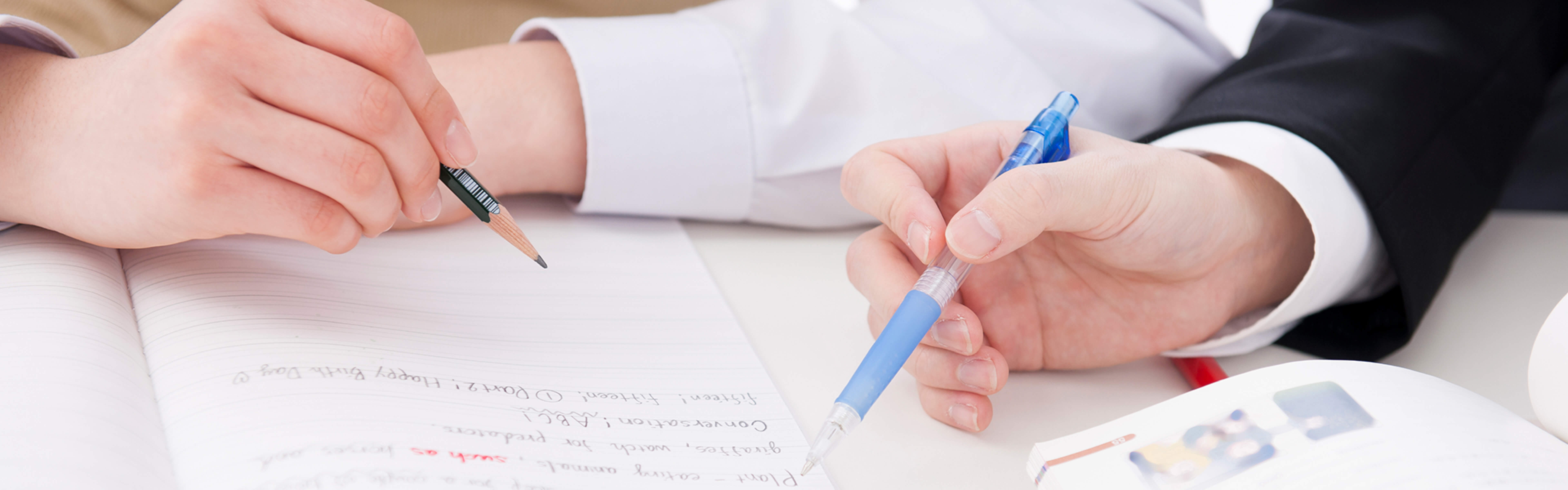ゲームで養われる「推測する力」

こんにちは!
今回は、私がこれまで体験してきたゲームと“推測力”の関係についてお話ししてみたいと思います。
私はこれまで、さまざまなゲームを遊んできました。
家族や友達と盛り上がったり、真剣勝負で競い合ったり、ときには一人で何度も失敗しながら挑戦したこともあります。
そんなゲームの中には、たくさんの思い出が詰まっています。
さて、私たちの身の回りには、いろんな種類のゲームがありますよね。
たとえば、「ボードゲーム」や「カードゲーム」などのアナログゲーム、そして「テレビゲーム」や「スマートフォンゲーム」などのデジタルゲーム。
これらは見た目や形式を変えながら、今でも新しい作品がどんどん生まれています。
多くの人にとって、ゲームは「娯楽」や「休憩」といったイメージが強いかもしれません。
でも私は、ゲームにはそれだけではなく、成長や学びの要素もあると感じています。
ゲームで身につく「推測力」とは?
中でも私が注目しているのが、「推測する力」です。
これは、ゲームの中でとてもよく使われる力だと思います。
たとえば、将棋。将棋には8種類の駒があり、それぞれ違った動きをします。
プレイヤーはそれらの動きを理解しながら、相手の次の一手を予想して駒を動かさなければなりません。
相手の考えを読み、どう動くかを推測することが勝負のカギになります。
これは将棋だけでなく、チェスやオセロなどの対戦型ボードゲームにも共通しています。
どのゲームも、相手の戦略を読み解こうとすることで、観察力や状況把握力も自然と養われていきます。
また、カードゲームでは少し違った形の推測力が求められます。
たとえば、トランプやUNOのようなゲームでは、相手の手札は見えません。
自分の手札や他のプレイヤーの表情・行動など、限られた情報から予測する必要があります。
これは、目に見える情報に頼るだけではなく、想像力や洞察力を使った推測が必要になります。

デジタルゲームにも広がる推測力
もちろん、これらの力はアナログゲームだけにとどまりません。
最近のデジタルゲームでも、同じように推測力を使う場面がたくさんあります。
たとえば、対戦型のシューティングゲームでは、相手の行動パターンを読むことが重要ですし、RPGでは謎解きやストーリーの中で「次に何が起こるか?」を予想する力が必要になります。
限られたヒントから選択肢を考えたり、次に進むための最善手を見つけたりといった場面は、まさに推測力の活躍の場です。
こうして考えると、ゲームを通して推測する力を自然と鍛えていることに気づきます。
そして、その力はゲームの中だけでなく、日常生活の判断や問題解決にも役立っていくのではないでしょうか?
「遊びながら学ぶ」という言葉がありますが、まさにゲームはその代表例かもしれませんね。
これからもゲームを楽しみながら、自分の中にある“考える力”を育てていけたらと思います。
また、ゲームには今回お話した“考える力”以外にも養われる様々な力があると思っています。
それがどのような力で日常生活にどのように繋がっていくのかに気付けたらと思います。
(宮下)
株式会社WALLESS(ウォレス)
〒910-0005 福井県福井市大手3丁目1-15 ビアンモアビル8F Tel.0776-89-1862
walless.net