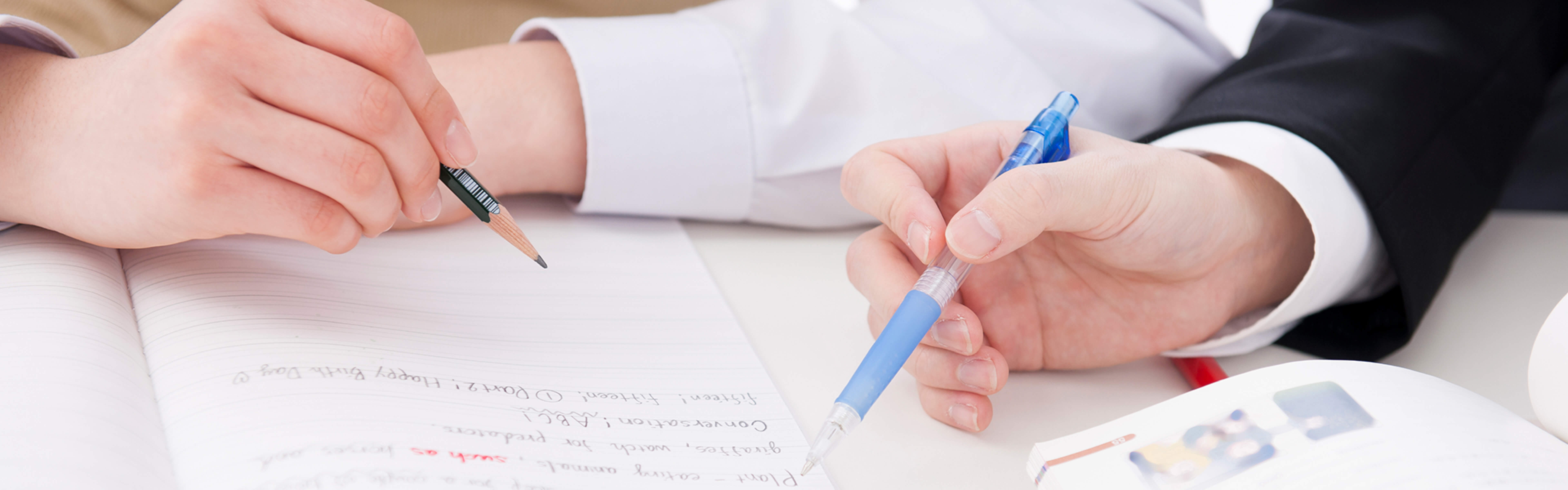

NEWS / BLOG
お知らせ・ブログ
避難訓練実施の報告

令和5年3月、ウォレスアカデミーにて避難訓練を実施いたしました。
当事業所はお子さまごとに来所される時間がそれぞれ違うため、全員での避難訓練は出来ません。
そのため、アカデミーのスタッフ一人ひとりがすぐに行動出来る体制が必要です。
ウォレスアカデミーでは、定期的に避難訓練を実施し、緊急時の対処法や避難経路を確認しています。
スタッフ同士で気付いた点を出し合いながら、入念に確認していきました。
①緊急時の役割・持ち物確認

スタッフ全員で緊急時の役割と持ち出す物を確認。
情報伝達係:状況確認、通報、周知、避難経路確保、連絡等
誘導係:お子さまの安全確認と声掛け、残留時の確認、名簿・緊急箱の持ち出し等
8階と5階の担当スタッフに分かれて状況確認。
各階で人数が揃い次第避難開始。
避難の際は、先頭と最後尾をスタッフ、間にお子さまをはさむようにして1列で移動。
②8階避難器具の操作確認

緊急時に窓の外へ出るための避難器具が8階のROOM4にあるため、実際に操作して確認。
③緊急時の避難経路確認

避難時は階段を使用。階段通路が確保されていることを確認。
避難場所である順化小学校まで歩いていき、待機場所となっている校庭の場所を確認。
避難訓練を終えた後は、注意点や緊急時の対応方法など、細かいところまで十分に話し合いました。
今年度は、会社全体で消防署による研修・講習を予定しています。
今後も、適宜スタッフ同士で意見を出し合って、適切な対処法を確認してまいります。
放課後等デイサービス・就労支援トレーニング・企業コンサルティング
株式会社WALLESS(ウォレス)
〒910-0005 福井県福井市大手3丁目1-15 ビアンモアビル8F Tel.0776-89-1862
walless.net
保護者様対象「ペア・トーク」のご案内

「こんなとき、どうしたらいいのだろう」「みんなは、どうしているのかな」「何かいい方法はないかな」など、考えたり、悩んだりすることが、毎日次々と起きますが、身近に相談できる人がいないこともあります。
そんなときは、同じような立場の保護者さま同士で、気兼ねなく話をしてみませんか?
今回は、お子さまではなく、保護者の皆さまを対象とした企画のご案内です。
その名も「ペア・トーク」今回で5回目の開催です。
これは、保護者(両親・ペアレント)の方にお集まりいただき、毎日の大変さやお困りごとなどを、保護者の皆さま同士で語り合って(トーク)いただくものです。
他の方と気持ちを共有することができたり、ヒントをもらって気づいたりすることができるかもしれません。
そんな気軽な気持ちでご参加いただけるとありがたいです。
参加希望される方は、以下の要領でお申し込みください。
【ペア・トーク】
■日程
令和5年5月14日(日)
10:00~11:30
■場所
ウォレス4階 フロア
■募集人数
6名~8名
■参加費
無料
■内容
10:00~11:20 自己紹介、フリートーク
11:20~11:30 アンケート・諸連絡等
■申し込み
お電話 0776-50-3623
または公式LINEよりお申込ください。
事務所スタッフへ直接のお申込みも受け付けております。
■申込締切
令和5年5月6日(土)
(定員に達し次第締め切らせて頂きます)
皆様のご参加を、お待ちしております。
放課後等デイサービス・就労支援トレーニング・企業コンサルティング
株式会社WALLESS(ウォレス)
〒910-0005 福井県福井市大手3丁目1-15 ビアンモアビル8F Tel.0776-89-1862
walless.net
卒業、進学する皆様へ

この度、ご卒業、ご進学される皆様、おめでとうございます。
4月からの新しい生活にワクワク、ドキドキされていることでしょう。
そんな皆様に、今日は就活で悩んでいる子へある方が贈った言葉を、私から皆様にも贈りたいと思います。
これから受験される方や、進路・就職を考える方も是非参考にしてみてくださいね。

“自分が今から選ぶものがどういう結果を生むかわからないのに選ぶタイミングだけくる。
正解はたくさんある。
どの会社(学校)を選んでもたいていの選択肢は正解。
数ある選択肢から「大吉を引こう」と思うことがあまり良くない。
大吉なんかなくて、たくさんある「吉」か「小吉」か「中吉」を引けばいい。
それを「大吉」にするのは入った後の自分自身。
どこに入ってもそれを正解にすることができる。
たくさん正解の選択肢があると思うことが大事。”
森岡毅(もりおか つよし)
経営難に陥っていたUSJをV字回復させたマーケター・実業家
「日曜日の初耳学」より
(近藤)
放課後等デイサービス・就労支援トレーニング・企業コンサルティング
株式会社WALLESS(ウォレス)
〒910-0005 福井県福井市大手3丁目1-15 ビアンモアビル8F Tel.0776-89-1862
walless.net
個性を大切に

「お子さまが得意なことや好きなことは何ですか?」という質問に対して、多くの保護者様はすぐにその答えを思い浮かべるでしょう。
では、お子さまの苦手なところ、出来ないところは何ですか?
「うちの子、〇〇ができなくて」
「〇〇ばかりしていて…」
などなど、短所の方がたくさんあがってしまうこともあるかもしれません。
しかし、長所と短所は表裏一体であり、環境や状況に応じて、短所が長所として見えることもあります。
例えば、「落ち着きがない」という短所は、見方を変えれば
「元気がいい」「いろんなことに気がつく」
という長所につながることもあります。
同様に、「自信がない」という短所は、見方を変えれば
「物事を慎重に考えることができる」
という長所として捉えられることもあります。

子どもの個性は、長所と短所を含むものであり、見方によって変わることがあります。
お子さまを他の子たちと同じ基準で評価することで、個性を失ってしまうこともあるかもしれません。
長所も短所もその子の個性として大人が受け止めてあげることで、お子さま自身が自分の持っている“個性”に気づき、その“個性”を大切に日常生活を送ることができるのではないでしょうか。
<担当:石倉>
放課後等デイサービス・就労支援トレーニング・企業コンサルティング
株式会社WALLESS(ウォレス)
〒910-0005 福井県福井市大手3丁目1-15 ビアンモアビル8F Tel.0776-89-1862
walless.net
呼吸法で気持ちを落ち着かせる~マインドフルネスpart.2~

前回のブログ「自分自身に“ご褒美”を贈りませんか?~マインドフルネスpart.1~」
では、自分へご褒美と一緒にマインドフルネスも贈りましょうということでした。
マインドフルネスとは
「いまこの瞬間」に注意を向け、思い浮かんでくる思考や感情を判断することなく、あるがままを受け入れること
そして、マインドフルネスを行うにあたり深くゆっくりとした呼吸方法で自分自身を穏やかにしていくこと、これをマインドフル呼吸法と呼びます。
自分の呼吸に焦点を当てることで、自分自身に集中して、どのようにしたいのかを決定するための落ち着きを得ることが出来ます。
この呼吸法は、練習を繰り返すことで、問題解決に対して“しなやか”になって、穏やかな自分自身を見出すことが出来ます。
この“しなやか”は、マインドフルな自分自身になるための4つの鍵となるスキルです。
「し」…深呼吸をして、心を整える
「な」…何が起きているか観察する
「や」…やりたいこと・大切にしたい価値に耳を傾ける
「か」…価値に沿った行動を決めて、行動する
マインドフル呼吸法では「し」と「な」のスキルを存分に使います。
では実際にマインドフル呼吸法を行ってみましょう!
ステップ1:呼吸に気づく
まずは、今この瞬間にどう呼吸しているのか、ただ気づくところから始めます。
片方の手を胸に、もう片方の手をお腹にあててください。
この位置で手をリラックスさせ、しばらくの間、自分の呼吸を観察しましょう。
息を吸う時、お腹にあてた手が押し上げられていますか?
それとも、胸にあてた手が押し上げられていますか?
あるいは、両方の手が少しずつ押し上げられていますか?
おそらく、胸にあてた手の方がより動いているのではないでしょうか?
普段、私たちの生活では、胸で息をする傾向があります。これは浅い呼吸です。
ステップ2:風船をふくらませる
ステップ2では、お腹で呼吸をする、深い呼吸を意識していきましょう。
手はそのままの位置に置いて、背筋を伸ばして座ってください。
お腹の中に風船が入っているのをイメージしてみましょう。
息を吸うと、お腹の中に風船がふくらんで大きくなり、お腹もふくれます。
そして、息を吐くと風船は小さくなり、どんどんしぼんであなたのお腹もへこみます。
このような呼吸をすると、胸の手はあまり動かないはずです。
息を吸うと、風船はふくらみ、大きくなります。
息を吐くと、風船はしぼみ、小さくなります。
息を吸う時にふくらむことをイメージして「1、2、3」、吐く時はしぼむイメージで「1、2、3」と数えると、呼吸に集中しやすくなります。
まずは、1分間この呼吸をおこなってみましょう。
それでも感情の渦の中にいるように感じたら、自分自身の様子を見ながら、1分より少し長い時間実践するようにしてみてください。
深い呼吸を実践することで「ちょっとスッキリしたな」と思えるようになります。
ステップ3:練習する
この呼吸法を意識して練習しましょう。
練習は気持ちが落ち着いているときにされるのがいいです。
普段とは違う呼吸法に慣れるまで時間はかかりますが、1回につき数分の練習を毎日することで、始めは分からなかった自分の呼吸や身体の変化に気づけるようになります。
毎日の練習は難しい…と思われた方は、決して無理はせず、ご自身がやりたいと感じた時に練習してみてください。
継続することで、穏やかで深い呼吸が意識できるようになります。

この呼吸法によって、考えや気持ちを消し去るものではないし、この呼吸法がゴールではありませんが、思い出した時にちょっと意識すると、穏やかに過ごせる時間が増えるかもしれません。
気持ちが高ぶるような時でも、より楽に呼吸できるようになると思います。
忙しい毎日の中でも、自分のために時間を作り、呼吸を整え、「いまこの瞬間」に集中する「ご褒美時間」を設けてみてくださいね。
きっと、モヤモヤや鬱々とした気持ちがラクになりますよ。
参考書籍:『セラピストが10代のあなたにすすめるACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)ワークブック』ジョセフ・V・チャロッキ、ルイーズ・ヘイズ、アン・ベイリー 著
<担当:瀧野>
放課後等デイサービス・就労支援トレーニング・企業コンサルティング
株式会社WALLESS(ウォレス)
〒910-0005 福井県福井市大手3丁目1-15 ビアンモアビル8F Tel.0776-89-1862
walless.net
